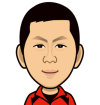記事公開日
最終更新日
私の作業の仕方

先日、柊さんが載せてくれた設計計算の作業の仕方をもとに、私のやり方を具体的に書いてみようと思います。
1.構造一般図を元にCADで構造図を作成
2.構造図から軸線図を作成
CADの操作で気を付けていることは以下になります。
・印刷したときの全体のバランス
→感覚的な要素なので言語化が難しいですが、上下左右対称か、余白のバランスはきれいか、などが気になってしまいます。
・寸法の合計
→CADの寸法のデフォは整数なため、小数点以下第一位で四捨五入されます。「寸法1500㎜」の内訳が「101㎜+1299㎜+101㎜(合計1501㎜になってしまう)」と表示されますが、実は「100.5㎜+1299㎜+100.5㎜」だった、ということがあるので最近確認するようにしています。
効率の良い操作方法については、まだ未熟で日々新しい発見があるので、もっと便利なやり方ないかな?を念頭に作業したいと思います。
3.構造図を使用して断面積と断面二次モーメントを計算する
最近私がミスをして気を付けるようになったことは、以下になります。
・桁の奥行B(m)は、実寸で計算する(1mあたりで計算しない)
・既設と新設が混在した構造物の場合、弾性係数を区別する
4.軸線図を使用して中間応力算出点を計算する
中間応力算出点の計算は、電卓で手計算して見直し確認の際に、CADにて寸法を測るようにしています。社長が仰っていた「CAD図を信用するな。測るな。」をなるべく意識しています。
5.荷重を計算する。下床反力か下床バネで計算するか確認する
荷重計算で気を付けていることは、以下になります。
・自重、土圧、揚圧力または下床反力以外の荷重を忘れない
→地上の荷重を忘れやすいため、上から順に追って荷重の要素を確認するようにしています。
・面積当たりの荷重なのか、一辺あたりの荷重なのか、単位を間違えないようにする
6.今までの算出結果を元にFRAMEを入力して、構造物に作用する応力を求める
FRAME入力後に1~6までをチェックする
こちらも最近ミスをして気を付けるようになったことは、
・下床ばねで計算する場合、支点は1点をX方向のみ極小のばねで固定する。
です。
7.FRAME結果データの応力を元にNOMOシートで鉄筋径を決める
応力度計算は苦手なので、気を付けることは全部があてはまりますが、ぱっと思いつくことは、
・桁の鉄筋被りは標準断面の主鉄筋分を考慮する
・既設鉄筋は、組合せ図を確認して鉄筋本数を入力する
・件名によってjの値を区別する
・許容値は使用コンクリート・鉄筋、荷重条件(長期か短期か)を考慮する
などです。
まだまだ上司に助けていただかないと作業を進められないので、全体を通して計算書を作るうえで「最終的に一人で計算書を作れるようになるためには」を意識して質問や作業をするようにしています。
思いつくまま列挙したので、読みにくいところもあったかもしれませんが、ご拝読ありがとうございました。
1.構造一般図を元にCADで構造図を作成
2.構造図から軸線図を作成
CADの操作で気を付けていることは以下になります。
・印刷したときの全体のバランス
→感覚的な要素なので言語化が難しいですが、上下左右対称か、余白のバランスはきれいか、などが気になってしまいます。
・寸法の合計
→CADの寸法のデフォは整数なため、小数点以下第一位で四捨五入されます。「寸法1500㎜」の内訳が「101㎜+1299㎜+101㎜(合計1501㎜になってしまう)」と表示されますが、実は「100.5㎜+1299㎜+100.5㎜」だった、ということがあるので最近確認するようにしています。
効率の良い操作方法については、まだ未熟で日々新しい発見があるので、もっと便利なやり方ないかな?を念頭に作業したいと思います。
3.構造図を使用して断面積と断面二次モーメントを計算する
最近私がミスをして気を付けるようになったことは、以下になります。
・桁の奥行B(m)は、実寸で計算する(1mあたりで計算しない)
・既設と新設が混在した構造物の場合、弾性係数を区別する
4.軸線図を使用して中間応力算出点を計算する
中間応力算出点の計算は、電卓で手計算して見直し確認の際に、CADにて寸法を測るようにしています。社長が仰っていた「CAD図を信用するな。測るな。」をなるべく意識しています。
5.荷重を計算する。下床反力か下床バネで計算するか確認する
荷重計算で気を付けていることは、以下になります。
・自重、土圧、揚圧力または下床反力以外の荷重を忘れない
→地上の荷重を忘れやすいため、上から順に追って荷重の要素を確認するようにしています。
・面積当たりの荷重なのか、一辺あたりの荷重なのか、単位を間違えないようにする
6.今までの算出結果を元にFRAMEを入力して、構造物に作用する応力を求める
FRAME入力後に1~6までをチェックする
こちらも最近ミスをして気を付けるようになったことは、
・下床ばねで計算する場合、支点は1点をX方向のみ極小のばねで固定する。
です。
7.FRAME結果データの応力を元にNOMOシートで鉄筋径を決める
応力度計算は苦手なので、気を付けることは全部があてはまりますが、ぱっと思いつくことは、
・桁の鉄筋被りは標準断面の主鉄筋分を考慮する
・既設鉄筋は、組合せ図を確認して鉄筋本数を入力する
・件名によってjの値を区別する
・許容値は使用コンクリート・鉄筋、荷重条件(長期か短期か)を考慮する
などです。
まだまだ上司に助けていただかないと作業を進められないので、全体を通して計算書を作るうえで「最終的に一人で計算書を作れるようになるためには」を意識して質問や作業をするようにしています。
思いつくまま列挙したので、読みにくいところもあったかもしれませんが、ご拝読ありがとうございました。